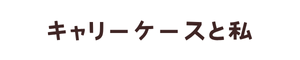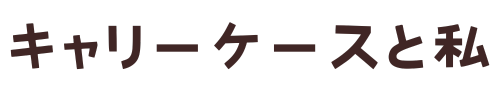冬になると雪国では、飛行機にも雪の対策が必要です。
特に北海道や東北、北陸の空港では、雪が滑走路や機体に積もることで運航に大きな影響を及ぼします。
自宅の駐車場や屋根の雪かきはスコップや除雪機を使うと思いますが、飛行機はそうはいきません。
お湯で希釈した特殊な液体を撒いて雪を溶かし、さらにコーティング剤で積雪を防ぐのが飛行機の除雪です。
厳しい環境でも飛行機が安全に飛び立てるのは、グランドハンドリングスタッフや整備の涙ぐましい努力があるからです。
本記事では空港で行われている「飛行機の除雪」について、その方法や特徴をわかりやすく解説します。
飛行機の除雪は何のため?
飛行機に雪が積もった状態では、空力性能が大きく損なわれるからです。
翼に雪や氷がついたままだと揚力が十分に得られず、離陸できなかったり最悪の場合バランスを崩して墜落の危険があります。
そのため出発前の機体には必ず、除雪(De-icing)と防除氷処理(Anti-icing)が施されます。

飛行機の除雪方法には2工程ある
飛行機の除雪には、大きく分けて2つの作業があります。
除雪(De-icing)
機体にすでに付着してしまった雪や氷を取り除く作業です。
デアイシングカーと呼ばれる特殊車両が使われ、ノズルから高温の液体を噴射して氷雪を溶かします。
車両のブームは自在に伸び、機体の高い位置にもしっかり対応可能です。

デアイシングで散布する液体はお湯と希釈して使用します(写真の白い部分は煙ではなく湯気です)。
その時の気温によって希釈度が変わり、気温が低いほど濃い液体を撒きます。
防雪氷(Anti-icing)
除雪後に再び氷雪が付着しないよう、機体表面に予防のコーティングを行うのがこの作業です。
防氷液を散布することで、一定時間機体を氷結から守ります。
どちらも非常に重要な工程で、安全運航の鍵となります。
防雪液は効果の持続時間が決められているため、かなりシビアです。
気温が低ければ低いほど持続時間も短く、滑走路まで行ったのに時間切れで再び駐機場へ戻ることもあります。
効果の持続時間はこちらで詳しく解説。
スピードと安全が命

飛行機の除雪作業は、限られた時間の中で迅速かつ的確に行われなければなりません。
実は到着~出発までの作業時間に除雪は考慮されておらず、雪が降った日は自ずと遅延します。
機体の大きさにもよりますが到着後、30分~1時間で折り返し出発をすることは夏も冬も変わりません。
また飛行機の出発時刻は機体が駐機場を離れることを指すので、除雪作業が発生するとどんどん遅れていくわけです。
なお出発時刻については、こちらで詳しく解説。
さらに防雪氷液のタイムリミットだけでなく、積み込み中の手荷物に液体がかかってはいけないので、出発直前の散布となってしまうのです。
そのため複数のデアイシングカーを稼働させたり、滑走路脇に専用の除雪用エリアを設けたりして、作業効率を最大化しています。
また気温や雪の状態に応じて使う液体の濃度を調整するなど、経験と判断力も求められる繊細な作業でもあります。
除雪専用エリアはこちらで解説
除雪作業の裏にはプロの技術が詰まっている
飛行機の除雪というと地味な作業と思われがちですが、実は航空の安全を守るために欠かせないカッコイイ仕事です。
現場ではグランドハンドリングスタッフや整備士、オペレーターたちが連携し、寒さの中で作業にあたっています。
飛行機が冬でも定時に、安全に空へ飛び立てるのは、こうした人たちの努力があってこそ。
次に冬の空港で飛行機を見かけたときは、ぜひその機体の美しい翼の裏にある除雪にも思いを馳せてみてください。
それでは良い旅を。