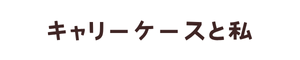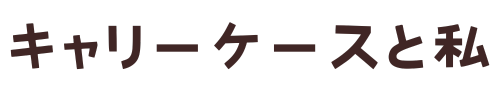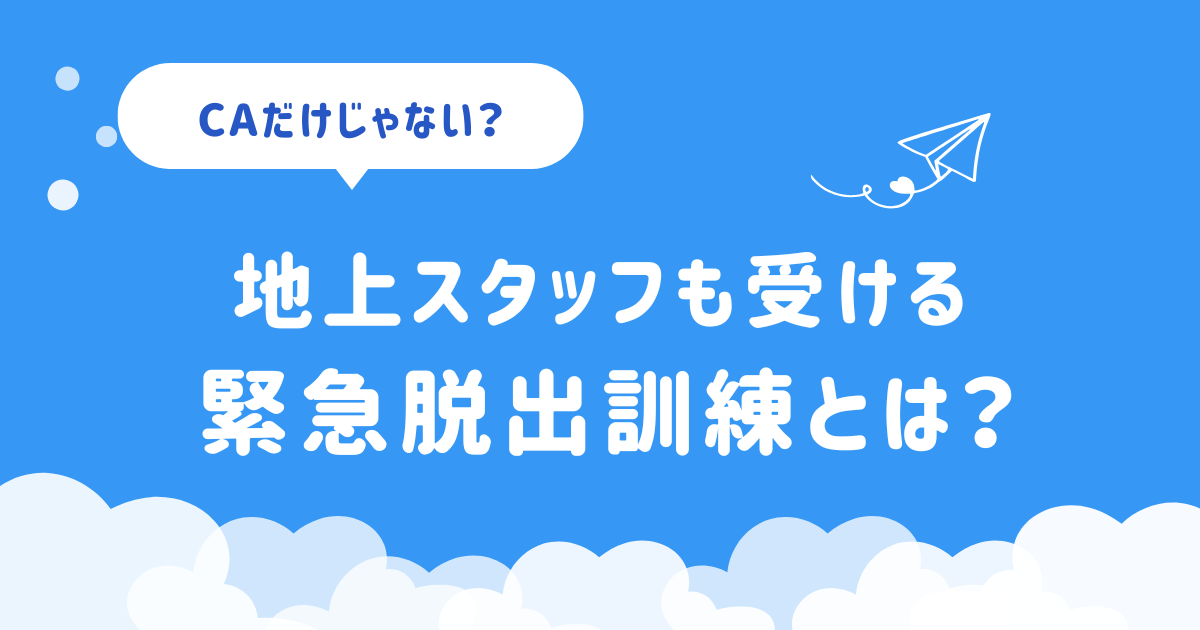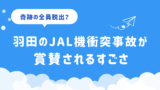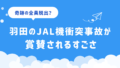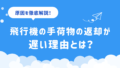飛行機に乗るとき、安全ビデオをちゃんと見ていますか?
非常口や酸素マスクの使い方、シューターを使った脱出の様子などが紹介されますが、「本当にあんなふうに脱出できるの?」と感じたこともあるかもしれません。
私は緊急脱出の訓練を受けたことがありますので、今回はそのときの体験をレポートします。
乗客も緊急時の重要な役目がある
訓練は機体の不具合により「緊急着陸が事前にわかっている」という設定で、乗り合わせた航空関係者としてCAの援助を行います。
役割は非常口の前でCAがドア操作する際に、押し寄せる乗客を制止する守るバリケード係。
他の社員と腕を絡ませて人の壁をつくり、「大丈夫!落ち着いて!」とパニック状態の乗客を制止します。
誰かが動けば一気に押し寄せてしまう緊張感の中で、「自分が冷静であること」の大切さを痛感しました。
脱出シューターは「滑る」より「ずり落ちる」感覚

安全ビデオではスーッと滑り降りているように見える脱出シューター。
でも実際は「思ったより滑らない…」というのが正直な感想で、シューターの表面がザラザラしていて摩擦が強く、ずり落ちるような感覚。
これは海上では救命ボートとして使うので、不安定なボートの上で滑ってしまうと危ないですよね。
一般の人も体験できる!JAL安全教室
こうした体験は、実は一般の方でもできる機会があります。
日本航空が羽田空港で行っている、「空育」というプログラムの中にあるJAL安全教室です。
中高生限定ではありますが実際に救命胴衣を着用してみたり、訓練施設の見学ができたりと、航空業界に憧れる生徒たちにとっては魅力的なプログラムであるはずです。
残念ながら2025年5月現在で開催を中断していますが、私も内容を見て「これだけでも緊急時の感覚が掴めるな」と感じました。
滑る怖さや足場の不安定さ、そして何より脱出シューターの存在感…これは映像だけでは伝わらない感覚です。
非常口のドア操作には“判断力”が求められる
非常ドアは誰でも勝手に開けていいわけではありません。
- 機長から「脱出開始」の指示を受ける
- ドアの外の安全を確認(火や障害物がないか)
- シューターが地面まで届いているか確認
ドア操作で最も重要なのが、ドアを開けても安全かどうかの判断です。
火が見えたら絶対に開けてはいけませんし、シューターが地面に届いていなければ脱出時に大けがになります。
ちなみに2024年1月に起きた羽田空港での衝突事故でJAL機の機内インターホンが使えなかったように、機長からの脱出指示が届かない場合はCAの判断でドア開けることもあります。
事故に関する記事はこちら。
パニックを抑える声かけは「大丈夫!落ち着いて!」
いざ脱出が始まれば、機内は大混乱のはず。
そんな中でやるべきことはドアに押し寄せる乗客を人間バリケードで阻止しながら、大きな声でパニックコントロールです。

大丈夫!!落ち着いて!!
いつも優しく笑顔のCAから想像もつかないくらい大声かつ無表情で言われるので、ビックリして「怖い」とか「どうしよう」など心配する余裕はないです。
このパニックコントロールの重要性も、訓練でしっかり学びました。
おわりに|「訓練を知ること」は、安心につながる
非常脱出なんて、一生に一度あるかないか。むしろない方がいいに決まっている。
でもその万が一のために、CAだけでなく地上係員や整備士も真剣に訓練しています。
こうした取り組みを知っていただくことで、飛行機に乗ることが少しでも安心につながればうれしいです。