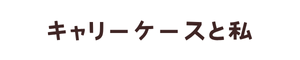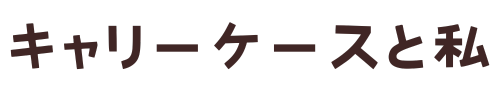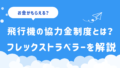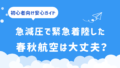2025年6月、三重県桑名市が土下座の強要や暴言、過大な金銭請求といった迷惑行為を「カスタマーハラスメント(カスハラ)」として正式に認定・公表しました。
これは2025年4月から始まった全国初の制度で、市は被害の深刻さを踏まえ次のような対応を明言しています。
- 行為者に対し、市長名で警告書を発出
- 改善が見られなければ、氏名や内容の公表も検討
今回の事案では、荷物の破損をきっかけに運送業の従業員に対して
- 暴言・脅迫的発言
- 土下座の強要
- 金銭・交通費の過大請求
といった行為が繰り返され、市は「社会通念を著しく逸脱した不当な要求」と判断。
カスハラ事案として公式に認定しました。
この記事では制度の背景・具体的事例・現場のリアルを通じて、私たちが向き合うべき現実と今後の課題を掘り下げます。
カスハラとは?なぜ問題なのか
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客が従業員に行う社会通念を逸脱した迷惑行為のこと。
【主な例】
- 長時間のクレーム対応の強要
- 威圧的な態度や怒号
- 土下座の強要
- 金銭・物品の過大請求
- 暴言・侮辱・差別的な発言
こうした行為は現場の従業員に深刻な精神的・身体的負担を与え、退職リスクの増大やサービスの質の低下にも直結します。
厚生労働省も2022年にガイドラインを発表しており、対策が急がれる社会問題となっています。
桑名市が全国初「カスハラ認定制度」を導入
桑名市は2025年度から、全国で初めてカスハラを組織的に認定・公表する制度を導入しました。
● 制度の目的
従業員がひとりで対応を抱え込まず、組織として迷惑行為に立ち向かい安全な職場を守るため。
● 主な仕組み
- 申請された案件を、市のカスハラ対策委員会が審議
- カスハラと認定された場合、市のホームページで概要を公表
- 加害者には市長名で警告書を発出
- 改善が見られなければ、氏名・内容の公表も検討
再発防止に向けて被害記録や対応履歴は庁内で共有され、従業員を組織で守る体制が構築されています。
認定されたカスハラ事案(2025年6月公表)
● 被害者
桑名市内の運送業に従事する従業員
● 発端
配送を依頼された荷物が破損していたことを理由に、荷主である行為者が「配送側の責任だ」と一方的に主張。
● 繰り返された迷惑行為
行為者は、次のような言動を複数回にわたり繰り返しました。
- 「馬鹿野郎」「嘘つき」などの暴言
- 「新聞社に言うぞ」との脅迫的発言
- 「土下座しているところを撮影するぞ」との侮辱
- 自宅への謝罪訪問を強要
- 呼び出し時の飲食代を請求
- 破損品の再購入に同行させ、交通費を請求
- キャンセルとなった予定に関する交通費の請求
- 弁済内容をメモに書かせるよう要求
● 市の判断と対応
市はこれらの行為を「社会通念を著しく逸脱した不当な要求」と明確に認定。
被害を受けた従業員の心理的負担は非常に大きく、組織として正式にカスハラ事案として対応しました。
今後、再発が確認された場合には:
- 市長名による警告書を送付
- 改善が見られない場合、氏名や詳細を公表
といった踏み込んだ対応が予定されています。
体験談|航空業界でもカスハラは日常だった
こうしたカスハラは、同じサービス業界では日常的に起きています。
私がかつて勤務していた航空業界でも、理不尽な対応を受ける場面は珍しくありませんでした。
● よくあるケース
特に多かったのが、乗客自身の遅刻による乗り遅れをめぐる逆ギレです。
- 「1〜2分遅れただけで乗せないなんて冷たい」
- 「いつもこの航空会社使ってやってるんだぞ」
- 「名刺出せ。会社に文句を言ってやる」
● 忘れられない体験
ある日、名刺を渡した直後に目の前で破り捨てられたことがありました。
その数分後には、何事もなかったかのように再び「名刺を出せ」と言われました(笑)。
● 本来守るべきルールへの反発
搭乗締切は、安全運航のために決められた厳格なルールです。
それを説明しても「サービスがなってない」と逆上され、怒鳴られた直後に平常心での対応を求められる理不尽さがありました。
航空業界の現場も、カスハラに無防備だったことは否定できません。
カスハラのない、誰もが安心して働けるサービス業界になることを願うばかりです。
まとめ
桑名市の制度はカスハラを「ただのトラブル」で済ませるのではなく、組織として明確に“これは許されない”と線引きする仕組みです。
この制度では:
- 被害内容を委員会で審議し、客観的に判断
- 認定された場合、市のホームページで事案を公表
- 行為者に対しては、市長名で警告書を発出
- 改善がなければ、氏名や内容の公表も検討
今回のような事案は従業員の尊厳や安全を脅かす深刻な問題であり、あらゆる業種に通じるリスクです。
この制度が全国に広がり、誰もが安心して働ける環境が守られる社会につながることを願っています。